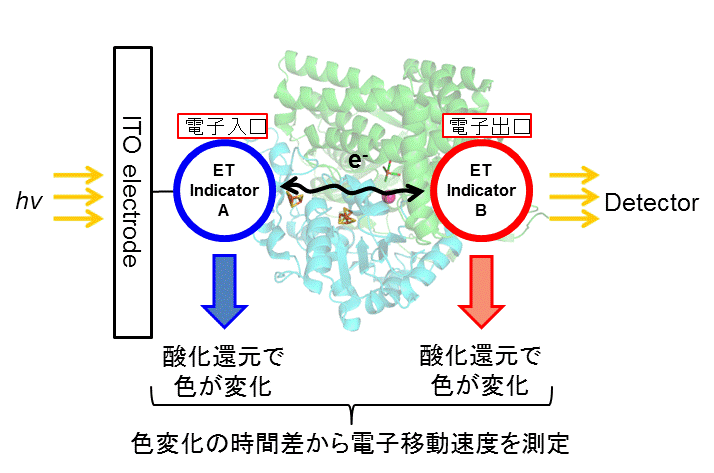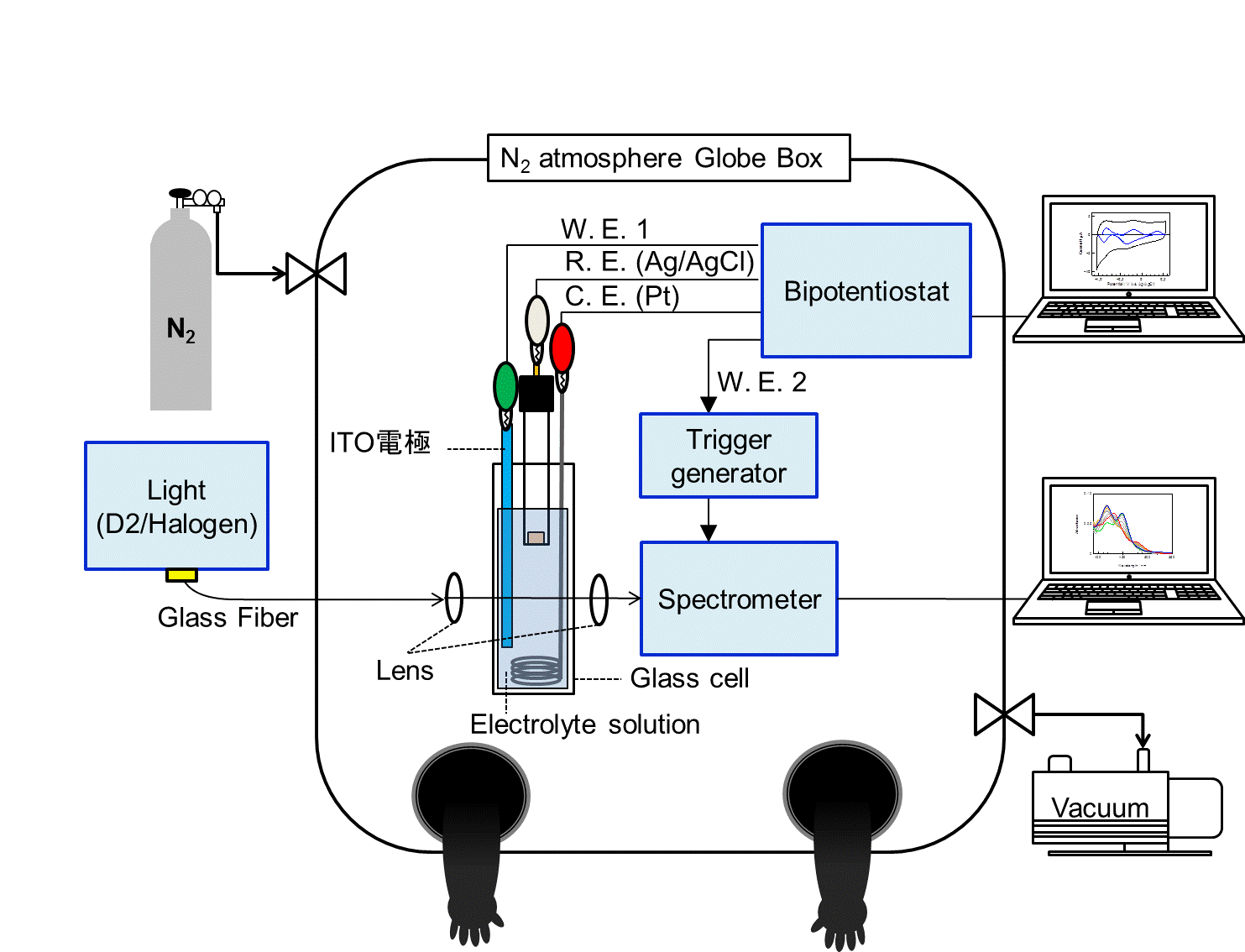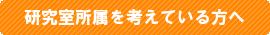①光エネルギーを電子へ
水溶液中の光励起電子移動
酵素反応を利用するとき,低い活性化エネルギーで反応が進行する一方で, 水溶液中では光増感剤から電子伝達体への電子移動反応が不利になるというジレンマがあります。 この電子移動の効率を高めるためには,電子移動の際に必要な溶媒かご(Solvent cage)形成速度が鍵となります。 電子移動の際のSolvent cage形成速度を高め,光励起1重項経由の電子移動が進行する分子の開発を行なっています。 分子を設計・合成し,ナノ秒レーザーフラッシュ法で解析を行なっています。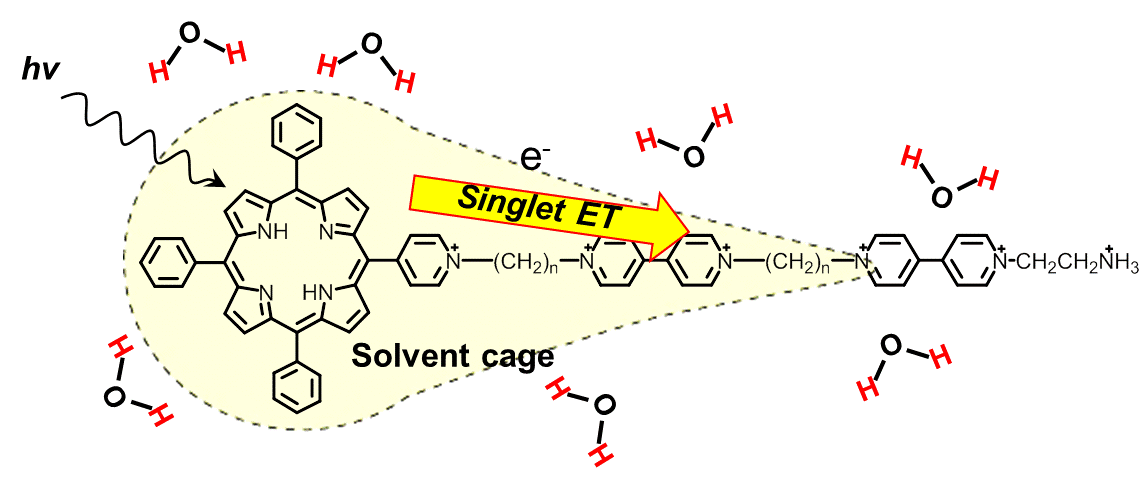
②ダイオード型電子伝達系の開発
ダイオード型電子伝達タンパク質シトクロムc3
非拡散の光駆動型酵素反応系を構築する場合,光と物質をつなげるためには電子伝達体の役割が重要になります。 酸化還元タンパク質シトクロムc3は4つの電子を高効率かつ選択的に受け渡すことができるダイオード型電子伝達体です。 シトクロムc3は分子内で電子を一定方向に流す電子移動の指向性と選択的にパートナーを認識する電子プール機構を有しています。 これらの機能に関わるシトクロムc3の4つのヘムの役割を明らかにし、電子伝達メカニズムを解明する研究に取り組んでいます。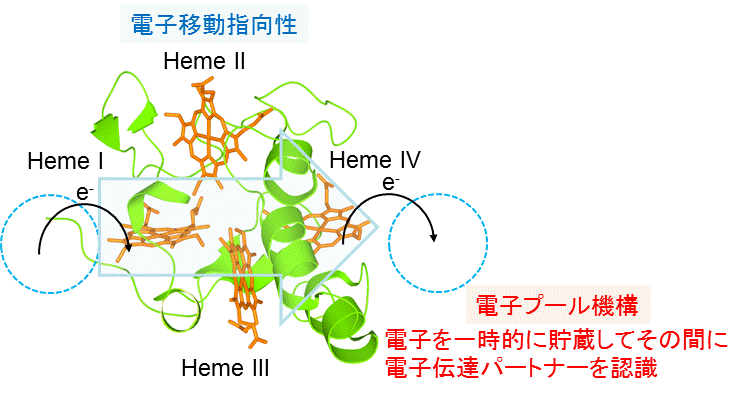
PFV(Protein Film Voltammetry)を用いたシトクロムc3の分子内電子移動測定
シトクロムc3の分子内電子移動メカニズムを明らかにするため、PFVを用いた測定を行なっています。 PFVでは,炭素電極にタンパク質を固定化することにより、酸化還元タンパク質と電極の直接電子移動を測定できます。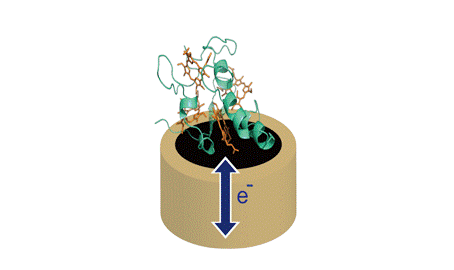
1.生体内で行なわれる酸化還元タンパク質の電子移動反応をin vitroで測定可能
→電極表面とタンパク質の間で抵抗が0に近い
2.微量の量(5μL以下)で簡単な操作で測定可能→単層電極のチャージによって簡単にタンパク質が吸着
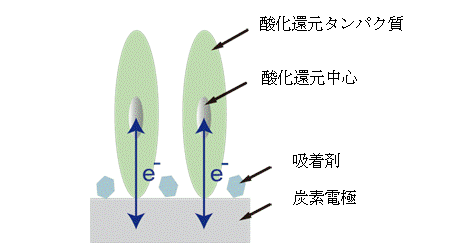
高感度EQCM(Electrochemical Quartz Crystal Microbalance)法を用いた
シトクロムc3の電子プール機構の解明
シトクロムc3の電子プール機構を測定するために高感度EQCM法を利用した測定を行なっています。
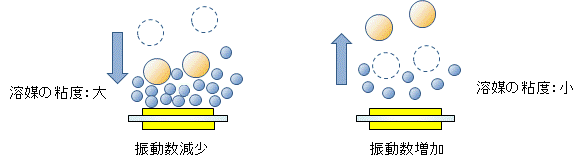
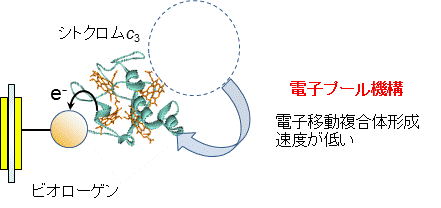
電気化学プローブを用いたシトクロムc3の電子移動指向性の測定
シトクロムc3の分子内の電子移動指向性を明らかにするため、 走査型電気化学顕微鏡のプローブ電極を利用した新しい測定法の開発を行なっています。 プローブ電極は直径12.5μmのディスク型微小電極であり、高さ方向の位置をナノメートルスケールでコントロール可能です。 したがって、基盤電極に固定化した分子とプローブ電極に固定化した分子の直接的な分子間電子移動を測定できます。 シトクロムc3の配向を制御することにより、シトクロムc3の電子移動指向性について調べています。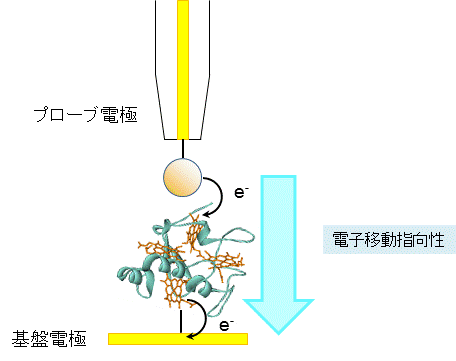
③電子から物質へ
高感度EQCM法を利用したタンパク質の分子間電子移動測定
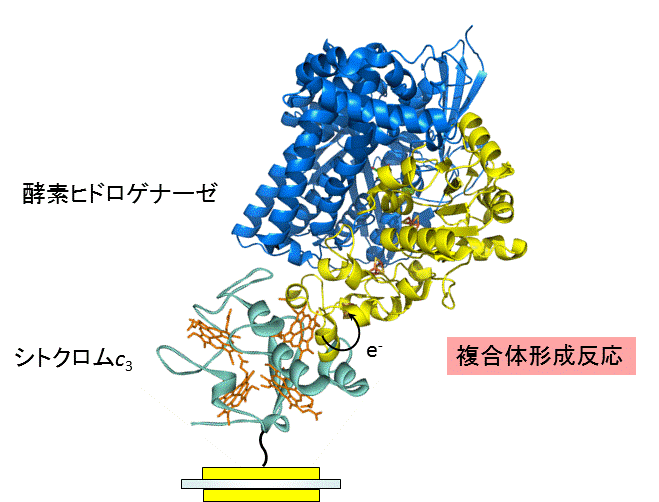
酵素分子内電子移動の新規測定法開発
酸化還元酵素の機能を最大限に利用するためには,酵素の分子内電子移動のメカニズムを明らかにする必要があります。 分子レベルで酵素分子内電子移動速度を測定するため,ITO透明電極と電子移動インジケーターを利用した新しい測定法の開発を行なっています。